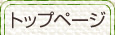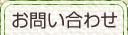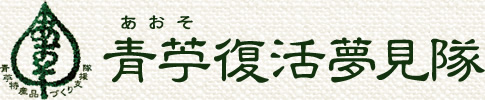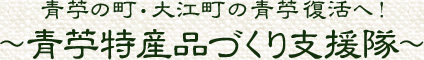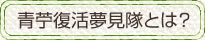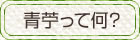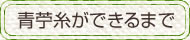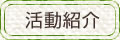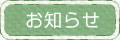SKYWARDに掲載されました!
青苧復活夢見隊:2015/12/02
ちょうど1年前になりますが・・・
『SKYWARD 2014年12月号』で「青苧復活夢見隊」が紹介されました!
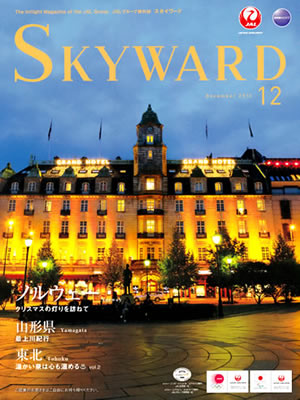
さまざまなメディアで紹介していただいているおかげで
『青苧の和』がどんどん広がっています♪
ありがたいことですし
励みになります!
さらに『青苧の和』が広がりますように☆
きゃりーライブ
青苧復活夢見隊:2015/11/13
番外編三部作の完結編です。
3月から楽しみにしていたきゃりーのライブ。
11月3日、仙台サンプラザにきゃりーが来てくれました。
当日はおばあちゃんから、小さい女の子、普通のお客さんからヲタクまで様々なファン層で、小さい女の子はコスプレしてるやら男も仮装してるやらでお祭り状態です。
見るものをてらいなく、非日常に連れて行ってくれるきゃりーの魅力が開演前から気分を盛り上げてくれます。
きゃりーと同い年のアメリカの歌姫、アリアナ・グランデはきゃりーの人気を「他とは違うから」と言っています。
「リスクを負ってでも他人と違うことをする姿はとても新鮮。音楽業界ではそれが大切」とのきゃりー評は、アメリカのショービジネスの最前線に生きるアリアナならではで、きゃりーが世界を魅了している理由はまさにそこなんだろうなあと思います。
ちなみに、アリアナは大の日本好きでもあり、日本語も勉強しているそうですが、きゃりーの曲の歌詞の意味が分からず翻訳ソフトにかけたことがあるようです。
一昨年、ポール・マッカートニーのコンサートに行ったときに感じたことですが、いくらこれまでに何度も曲を聴いていても、やはり英語の曲を一緒に歌うことは難しいんですよね。
サビの部分とかゆっくりした曲くらいでしか一緒に歌えない。
それが、ポールをどれだけ好きでも一緒になり切れないもどかしさを感じさせるんですが、日本語だとそういうことは全くない。
何しろCDを毎日聴いてるんですから、嫌でも歌詞を覚えるし、カラオケで歌いなどしたら、それこそあっという間に頭に入ります。
そらできゃりーと一緒に全部の曲を歌えるんですから、これほど楽しいことはない。
アリアナが翻訳ソフトにかけてまで知りたかった歌詞が全部分かる。
造語や、言葉遊びの意味まで全部分かる。
これまで海外アーティストの海外のファンに対して抱いていた羨望が、今度は優越感に変わるわけですから、これまた楽しい。
言葉が通じるというのは、大変楽しいです。
会場の仙台サンプラザはステージに向かって客席が円形に配置されているため、ステージに対して斜めの席は数人掛けになっています。
私は二人掛けの席で、私の前の人は一人掛けでした。
一人掛けの彼は広いスペースで気持ち良くヲタ芸(ファンが曲に合わせて独特の踊りや動きをすること)をするもんだから、こちらもそれにつられてどんどんノっていってしまいます。
なにせきゃりーを見る視線の手前には必ず彼がいて、2時間弱の間ずっと二人を同時に見ているわけですから、ヲタ芸を2時間鑑賞したと言ってもいいくらいです。
きゃりーラブの目線で彼を視界に捉え、なおかつ彼がまた私をどんどんノセてくれるという状況では、きゃりーと言えばヲタ芸がインプットされたとしても致し方ありません。
実際、ヲタ芸もいいなあと思いました。
出来れば覚えてみたい。
そうして歌って踊っての夢時間はあっという間に過ぎていきました。
これまで身近な人に「きゃりー大好き」「きゃりーのコンサートに行く」と言うと、必ず「えっっ!」とびっくりされましたが、きゃりーは最高です。
同時代にいながらきゃりーに触れないのはもったいない。
最近はジムに通ったり、食事制限をしたりしてダイエットに励んでいるようですが、それなら、半日断食をお勧めしたいです。
私自身は今月から一日一食を時折試してますが、朝食抜きの半日断食なら負荷も少ないですし、手軽に始められるんではないかと思います。
まあ、きゃりーの場合は生活も不規則だろうし、まだ若いから半日断食でも抵抗があるかもしれませんが、長く活躍してもらうには最高の方法だと思います。
芸能界にはそういったことをしている先輩も多いでしょうから、機会があれば始めてもらって、長く楽しませてもらいたいものです。
また、来年も見に行くよ~。
海難1890
青苧復活夢見隊:2015/10/24
日本・トルコ合作映画『海難1890』の舞台挨拶付先行上映会に行ってきました。
タイトルの『海難1890』というのは、1890年(明治23年)9月にトルコの軍艦エルトゥールル号が和歌山県樫野崎沖で座礁した事故のことを指しています。
大島村(現在の串本町)樫野の住民たちは嵐の中、総出で救出、介抱に当たり、69名の乗組員を救助しました。
587名の乗組員は死亡あるいは行方不明となりましたが、この事故は当時の新聞でも伝えられ、全国から多くの義捐金、弔慰金も集まっています。
翌1891年1月には日本海軍の艦によって乗組員たちは無事、本国に送り届けられました。
この出来事はトルコの教科書によって子供たちに教えられ、現在に続く、トルコ国民の日本への好感の大きな一因になっています。
時は流れて1985年、イラン・イラク戦争でイラクのサダム・フセイン大統領がイラン上空を飛行する航空機に対して期限付き無差別爆撃を宣言し、イラン在住の邦人はイラン国外に脱出出来ない危機的状況になりました。
当時は法律によって自衛隊機による救援が出来ず、また、ナショナルフラッグキャリアたる日本航空も「安全が保証されない」として、救援の臨時便を見送ったのです。
各国の人々が次々とイランから避難する中、野村イラン駐在大使はトルコの駐在大使に窮状を訴えます。
要請を受けたトルコ航空は自国民救援のための最終便を二便に増やし、日本人を優先的に便乗させ、期限ぎりぎりでイランを脱しました。
飛行機に乗れなかったトルコ国民は陸路自動車でイランを脱出、邦人は全員がトルコ経由で無事に帰国を果たしています。
この史実を基にした物語なわけですが、作中、トルコの皆さんが自分たちを後回しにしてでも、邦人の救出を優先させてくれた場面には心底「ありがとうございます!」と胸を込み上げてくるものがあります。
日本人ならあの場面で涙を堪えることは難しいでしょう。
自分自身が助かったわけでもないのに、本当に有難いと感じるのは一体何なのでしょう。
日本側がトルコの乗組員を助ける場面では、スクリーンに引き込まれながらもある意味では当然と思って観ていますが、立場を置き換えて、自分がトルコ人になったつもりであの場面を観ると、やはりとんでもなく有難いと思わずにはいられないと思います。
ある本によると、人間に生まれる確率は、「目の見えないウミガメが100年に一度海面に顔を出します。そのとき、ちょうどウミガメの頭が入るほどの穴があいた板きれが海面に浮いていて、その穴にウミガメが頭を突っ込むほど」のことなのだと言います。
お釈迦様がそう話したそうです。
そうすると、人間に生まれて生きていること自体が「有難い」ことで、今こうして存在していることはまさに奇跡と言えるのです。
私は職業柄、いつも植物や虫、微生物や動物を意識して生活していますが、いくら蚊やアリにも大事な役割があると思っても、やはり彼らに生まれず人間でよかったと思います。
お釈迦様の例え通りならば、彼らは人間に生まれたくてしょうがないのかも知れない。
それなのに彼らは特に見返りも求めず、淡々と役割を果たしている。
でも、人間はなかなかそのことが難しい。
トルコの乗組員を救った村人たちも、まさか、95年後にそのような出来事が起ころうとは思いもしなかっただろうし、そもそも何か見返りを求めたわけではないでしょう。
ただ、純粋に善意と真心があったのだと思います。
人間の世の中に暮らしていると、どんなにいい人でも誰かに何かをしてあげれば、「あの人に何々してあげた」と思っているだろうし、中にはそのことを勘定していて、「あの人にあれをしてあげたのに、あの人は何もしてくれない」と言って憤慨したりします。
それは善意のようであって、実は損得勘定に過ぎない。
ある農家の先輩も、「自分に何かをしてくれた人にお返しするというのは、それはそれでいいことだけれども、何か取引のようでもあるから、自分がしてもらったことをまた別の誰かにしてあげた方が良い」というようなことを話してくれました。
二人の間で恩を返すというのは、二人の間で完結してしまいますが、他の誰かにしてあげると、それはいつまでも続いていくことになります。
見返りを求めないというのは、私はエジプトにいるときに強く実感しました。
レスリングを教えていた子供たちに自分の着なくなった服をあげた時、彼らは私には一言も礼を言わなかった。
その代り「アッラーありがとう」と言ったのです。
彼らはイスラム教徒ですから、アッラーに感謝したのです。
彼らの世界だと、この世のすべてはアッラーが動かしていますから、自分たちに服をくれたのもアッラーの仕業であるということなのでしょう。
私も特別見返りを求めたわけでなかったものの、お礼の言葉さえもなかったことは少々ショックでした。
「お礼の言葉」くらいのことは当然心のどこかで期待していたのです。
今だと彼らの世界も理解できますから、特に何も思いませんが、その時には「ああ、お礼の言葉さえも期待しないで、自分がやろうと思ったことをすればいいのだな」と思いました。
確かにあり得ないくらいの確率で存在し、生きているわけですから、アッラーが全てを動かしていると言えるのです。
イスラム教徒でなければアッラーを別の言い方に置き換えてもいいでしょう。
自分の存在自体が数えきれない先祖の連なりから生まれ、今現在も身の回りのものやことを、顔や名前も知らない人たちのお陰で整えてもらっていることを考えると、人は気付かずして、いつも他の誰かのために動いていると言えます。
今回の映画でも、トルコの人が昔の恩を返してくれたと見るのではなく、善意や真心が時空を超えて別の誰かにつながったと見るべきだと思います。
そういう風に見てこそ意義がありますし、私もまたそのようにして生きていきたいと思っています。
- 焼畑2025
- 卒業研究報告会
- ひなまつりと青苧研究報告会のお知らせ
- だんごさし
- 完売のおしらせ
- 小正月行事開催のお知らせ
- テレビ放映のおしらせ
- さくら と 御膳 と 芋煮会 ③
- さくら と 御膳 と 芋煮会 ②
- さくら と 御膳 と 芋煮会 ①
- 2025年5月 (1)
- 2025年4月 (1)
- 2025年3月 (1)
- 2025年1月 (2)
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (1)
- 2024年7月 (1)
- 2024年6月 (1)
- 2024年5月 (1)
- 2024年4月 (1)
- 2024年3月 (1)
- 2024年1月 (3)
- 2023年12月 (3)
- 2021年5月 (1)
- 2021年2月 (1)
- 2021年1月 (1)
- 2020年6月 (4)
- 2019年5月 (1)
- 2019年1月 (2)
- 2018年11月 (3)
- 2018年7月 (1)
- 2018年6月 (1)
- 2018年5月 (1)
- 2018年2月 (2)
- 2018年1月 (4)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (1)
- 2017年5月 (1)
- 2015年12月 (2)
- 2015年11月 (1)
- 2015年10月 (1)
- 2015年6月 (1)
- 2015年5月 (1)
- 2015年4月 (2)
- 2015年3月 (2)
- 2015年2月 (3)
- 2015年1月 (1)
- 2014年12月 (1)
- 2014年10月 (2)
- 2014年9月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年4月 (1)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (1)
- 2013年12月 (1)
- 2013年11月 (2)
- 2013年10月 (2)
- 2013年7月 (3)
- 2013年6月 (3)
- 2013年5月 (5)
- 2013年4月 (2)
- 2013年3月 (1)
- 2013年2月 (1)
- 2013年1月 (1)
- 2012年12月 (1)
- 2012年11月 (1)
- 2012年10月 (1)
- 2012年9月 (1)
- 2012年8月 (2)
- 2012年7月 (1)
- 2012年6月 (1)
- 2012年5月 (2)
- 2012年4月 (1)
- 2012年3月 (1)
- 2012年2月 (2)
- 2012年1月 (4)
- 2011年12月 (3)
- 2011年11月 (1)
- 2011年10月 (4)
- 2011年9月 (3)
- 2011年8月 (2)
- 2011年7月 (4)