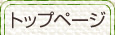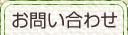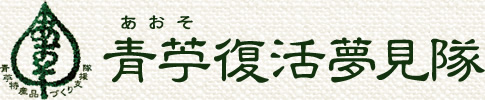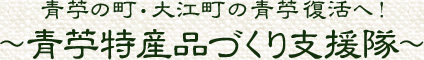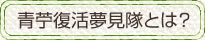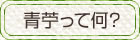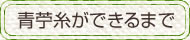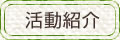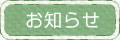人の世界も多年草
青苧復活夢見隊:2013/04/29
根っこの世代交代ということで畑一畝分(10m×10m)の株分けをしました。
青苧は地下茎で増えていく多年草ですが、8年くらいすると良質の繊維が取れなくなります。
そうなる前に6年目の今年、一部の根を掘り起こして別の畑に移植することにしました。
一株の根っこも木質化したような塊の根っこ、ゴボウのような根っこ、柔らかく芽の付いた根っこ、毛細根と形状も様々で、役割もそれぞれ違うのでしょう。
ちなみにゴボウのような根っこの皮を削いでみるときれいな白色で、山芋のようなぬめりもあったので試しにかじってみたところ、アクが強く繊維質も舌に障る感じであまり誉められたものではなかったです。
採った根っこは15cm程度の長さにそろえ、すぐさま別の畑に移動して植えました。
今日も若者が3人助っ人に来てくれたので作業もはかどりました。
大人数でやる畑仕事は作業の進むのが早くて楽しいです。
あれを一人や二人でやるとなると、途中でやんだぐなる(嫌になる)こともありますが、人手があると苦になりません。
畑仕事っていうのはやっぱりみんなでやるもんですね。
仕事はぴったり12時に終わって、そのまま畑で村上代表の作ったおにぎり、青苧餅、山菜のこごみ、手作りおかずを皆でいただきました。
畑でみんなで食べるごはんは最高!
そこでまた素敵な出会いがあったので、追々ブログでもご報告できるかもしれません。
私はいつも畑で起きていることを観察、考察し、家に帰ってはそれに関することを調べたり、本を読んだりして日々の仕事の備え、蓄えにしていますが、自然に学ぶということは終わりのないもので、今自分がどの程度分かってきているのかということもはっきりとは分かりません。
農業は馬鹿でも出来るし、反対に天才でも極めることは出来ない奥の深い世界だなあと思います。
一つの事象の原因、結果が一つということはなく、無数の条件が複雑に絡み合っている世界だから面白いのだろうなあと思います。
その中にいると人間の出来ることは本当にちっぽけなものです。
でも人が手を加えないと、人々に受け入れられるものは仕上がらない。
そこがまた面白いとこなんです。
私の周りにもこれまでの自分の仕事、人生を転換して農業をやりたいという人が増えてきました。
自分のやっていることが本当に生産的な仕事なのかとか、まだ充分使えるものを捨てさせて新しいものを買ってもらうということが本当に世の中のためになるのかとか、金融や広告など実体のないものを売っているとモノを作る仕事に憧れるとか、理由は人それぞれです。
でもその根底には自分が本当に満足できることをやりたい、社会的にも自分の中でも嘘のないことをやりたいという欲求があるように思います。
一度きりの人生、思いっきり自分のやりたいことやりたいですよね。
毎日畑にいるとPM2.5やら黄砂やら色々飛んできて、安穏としてはいられないご時世ではありますが・・・。
さて、次回は焼畑の様子をご報告します。
久々にお知らせ欄にも書きました。
興味のある方のご参加お待ちしています。

キテます。
青苧復活夢見隊:2013/03/02
今回は和紙とシンクロニシティのお話。
青苧を使った和紙の研究に取り組んでいる、東北芸工大文化財保存修復研究センターの大山龍顕研究員から報告会のご案内をいただいたので、猛烈な風に雪が舞い踊る中、午後から隊長夫妻、栽培部長と一緒に東北芸工大に行ってきました。
今回の発表テーマは「青苧と和紙からみた地域文化力の向上」ということで、青苧和紙の制作に関わる技法も報告の一つの柱でした。
青苧和紙は昨年から西川町の紙漉き職人三浦一之さんに制作を依頼しており、様々な試行錯誤の末、最近形が出来上がりました。今春、大江町の本郷西小学校では卒業証書として使用されます。
残念ながら本郷西小学校は今年度で廃校となりますが、その最後に青苧和紙の卒業証書をお渡しできるというのは夢見隊としてはなんとも言えない気持ちです。
技術的なことを言うと、和紙に使う青苧はきちんと表皮を取ったものでないといけません。そのためには糸にするのと同様、苧引きが必須となるのですがそれは大変。
糸にするのなら苧引きは絶対にやらなければならないことなのでそれなりの覚悟も出来ますが、見た目に繊維が分からないくらいになってしまう紙ではそこまでの気持ちを持つことは容易ではありません。
そこで大山さんは独自に苧引きせずともよい方法を研究し、ついにこの難問をクリアしてしまいました。
詳しくは企業秘密ということにしておきますが、苧引きの労力を知る身としてはそれは夢のようなお話です。
つまり、刈り取って皮を茎から剥いでしまえば、あとは大山方式によって真っ白な繊維が取り出せてしまうというわけです。
これは苧引きを省略した商品化ということを考えた場合、天恵のようなもので、私が考案したわけでもないのに誇らしくさえ思えます。
大山方式がいろいろな試験によって磐石のものとなれば、青苧栽培はまた一歩新たなステージに突入するでしょう。
大山さんは引き続き青苧と和紙の可能性について活動予定ということですので、ぜひともお力をお貸しいただきたいところです。
ところで、私は最近シンクロニシティづいてます(シンクロニシティ=共時性:意味のある偶然の一致のこと)。
大山さんが報告の中でデザイナーの梅原真さんのこともお話されましたが、私は今朝の新聞の特集で梅原さんのことを見ていました。それまで知らなかった人の名前を全く違う場所で一日に二度も聞くことは滅多にないでしょう。
最近では山寺のことでも友人とシンクロしました。
この他、なぜか年明けからやることなすことすごくタイミングがいいのです。
友人曰く、地球は新たな26000年の周期に入ったとのことですので、私のサイクルもそれに連動してきているのかもしれません。
それに今年は史上三回目といわれる出雲大社(5月)と伊勢神宮(10月)の同時式年遷宮の年ですので、霊力の発動も半端ないはずです。
皆さんの周りにもシンクロニシティが起きているでしょう。
そうした動きは一人より大勢のほうが強いでしょう。
望めば叶うような気がします。
今、冬と春が綱引きしていますが、春が来た暁には冬は去るのです。
青苧のことももっと広く知ってもらうように検討中ですので、今年は大きなステップが出来そうな気がします。
成功することを恐れず、この流れを大事にしたいと思います。
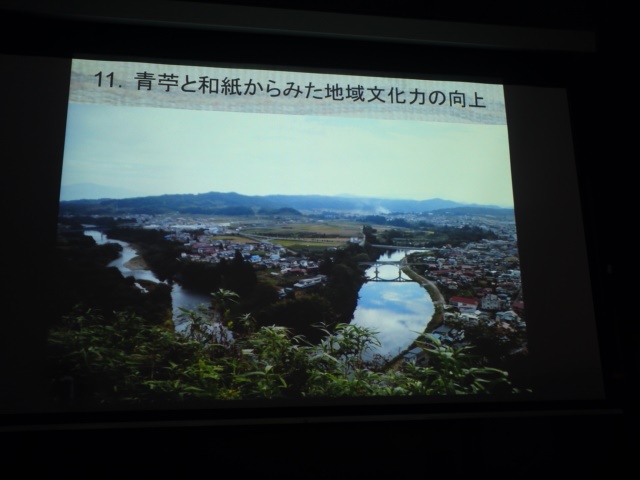
これは何の壁
青苧復活夢見隊:2013/02/23
世の中には意味の良く分からない規則があるものです。
青苧入りアイスクリーム出来てます。
成分分析もして、鉄分やビタミンなど様々な栄養成分が高いことも分かりました。
量はアイスタンク2リットル中、青苧は20グラムほどと微々たるもの。
青苧うどんやひやむぎは既に商品化して販売しています。
うどんなどと違ってアイスは加熱しないからというような、加熱非加熱も問題にはならないようです。
それなのに、アイスとなると「食歴がないから」ということで許可が下りないのです。
もともと青苧は繊維部分を取るのが目的で、その方面での歴史は文献などを辿れば何百年と続いてきたことを証明出来ます。
ただ、葉っぱや茎を食べていたという記述は見られません。
だから食べても問題はないのだけれど、歴史がないということで許可されない。
なんともやるせない話です。
やるせない話だけれども、じゃあどうしたらいいのかなということで、米沢女子短期大学の齋藤寛子先生にお話を伺いに行ってきました。
食歴と言われてもないものはないのだから、その点では先生もお困りでしたが、他の商品開発についていろいろとヒントをいただきました。
先生が注目されたのは鉄分。
鉄分含有が多いといわれるほうれん草に比べても青苧はさらに多くの鉄分を含んでいます。
それに注目して、女性向けの商品が作れないか。
それから、青苧はよもぎなどと同じように食品に練りこんで使えますが、よもぎのような香りはありません。
それなら逆に香りがないことを売りに出来ないか。
その他にもいくつか先生ならではの提案をしていただきました。
いろいろな人の話を聞くというのは、視点が違って勉強になるものです。
東京メトロと都営地下鉄のホームを隔てる地下鉄九段下駅の「バカの壁」。
猪瀬都知事の提案で現在撤去中です。
壁を作るも壊すも人次第。
初めから壊すものなら作らないほうがよっぽどましです。
行政側の人はいつでも利用者の立場になって余計な壁は作らないで欲しいものです。
- 焼畑2025
- 卒業研究報告会
- ひなまつりと青苧研究報告会のお知らせ
- だんごさし
- 完売のおしらせ
- 小正月行事開催のお知らせ
- テレビ放映のおしらせ
- さくら と 御膳 と 芋煮会 ③
- さくら と 御膳 と 芋煮会 ②
- さくら と 御膳 と 芋煮会 ①
- 2025年5月 (1)
- 2025年4月 (1)
- 2025年3月 (1)
- 2025年1月 (2)
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (1)
- 2024年7月 (1)
- 2024年6月 (1)
- 2024年5月 (1)
- 2024年4月 (1)
- 2024年3月 (1)
- 2024年1月 (3)
- 2023年12月 (3)
- 2021年5月 (1)
- 2021年2月 (1)
- 2021年1月 (1)
- 2020年6月 (4)
- 2019年5月 (1)
- 2019年1月 (2)
- 2018年11月 (3)
- 2018年7月 (1)
- 2018年6月 (1)
- 2018年5月 (1)
- 2018年2月 (2)
- 2018年1月 (4)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (1)
- 2017年5月 (1)
- 2015年12月 (2)
- 2015年11月 (1)
- 2015年10月 (1)
- 2015年6月 (1)
- 2015年5月 (1)
- 2015年4月 (2)
- 2015年3月 (2)
- 2015年2月 (3)
- 2015年1月 (1)
- 2014年12月 (1)
- 2014年10月 (2)
- 2014年9月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年4月 (1)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (1)
- 2013年12月 (1)
- 2013年11月 (2)
- 2013年10月 (2)
- 2013年7月 (3)
- 2013年6月 (3)
- 2013年5月 (5)
- 2013年4月 (2)
- 2013年3月 (1)
- 2013年2月 (1)
- 2013年1月 (1)
- 2012年12月 (1)
- 2012年11月 (1)
- 2012年10月 (1)
- 2012年9月 (1)
- 2012年8月 (2)
- 2012年7月 (1)
- 2012年6月 (1)
- 2012年5月 (2)
- 2012年4月 (1)
- 2012年3月 (1)
- 2012年2月 (2)
- 2012年1月 (4)
- 2011年12月 (3)
- 2011年11月 (1)
- 2011年10月 (4)
- 2011年9月 (3)
- 2011年8月 (2)
- 2011年7月 (4)